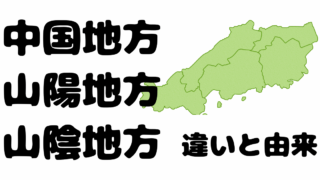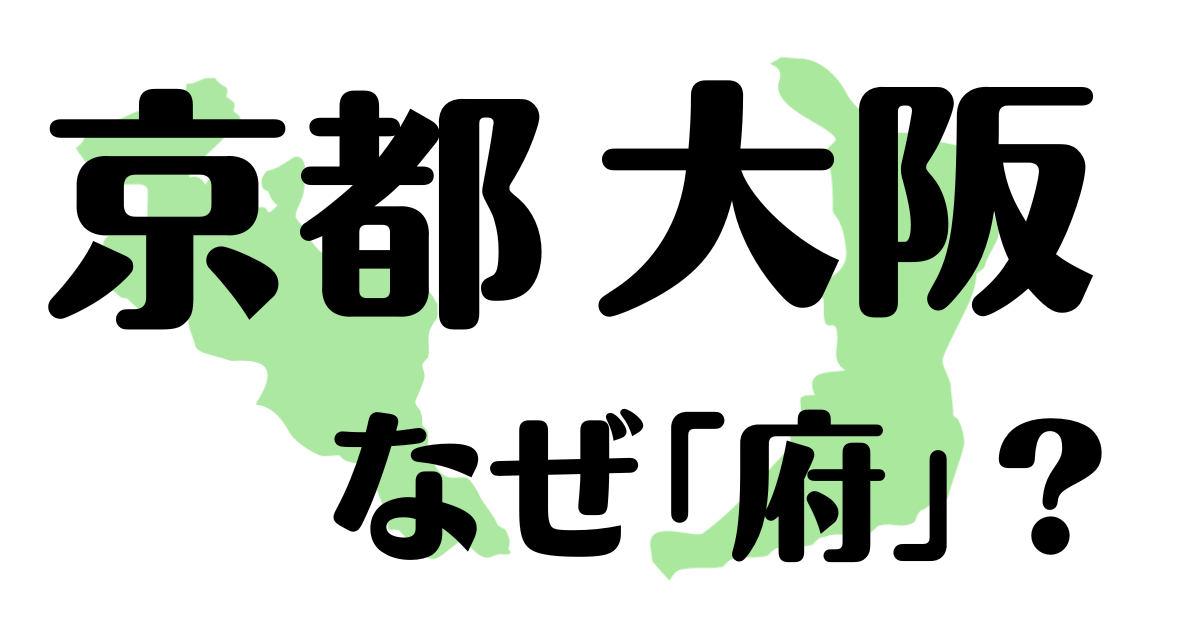「大阪」はなぜ“阪”? “大坂”から“阪”になった理由とは
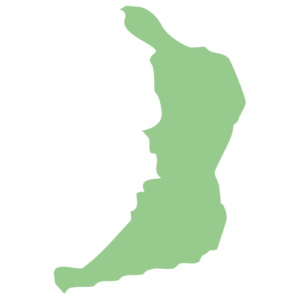
「大阪」という地名、よく見ると「坂」ではなく「阪」と書きます。
しかし、もともとは「大坂(おおさか)」と書かれていたことをご存じでしょうか?
この記事では、「大坂」から「大阪」へと変わった理由、そこに込められた歴史的背景や意味を詳しく解説します。
もともとは「大坂」だった?
現在の「大阪」という地名は、もともと室町時代末期に「大坂」と書かれていたのが始まりとされています。
この「大坂」という表記は、戦国時代の文献や豊臣秀吉が築いた「大坂城」の名にも使われていました。
つまり、かつては“坂”の字が正式な表記だったのです。
“坂”が“阪”に変わったのは明治時代
「大坂」から「大阪」へと文字が変わったのは、明治維新のころといわれています。
明確な記録は残っていませんが、当時の政府文書などが一斉に「大阪」表記に統一されました。
その理由には諸説ありますが、有力なものをいくつか見ていきましょう。
① 「坂」が「士が反(さか)う」に通じるのを避けた説
最も有名なのが、「坂」という字が「士(武士)が反(そむ)く)」という文字構成に見えるため、縁起が悪いとされて「阪」に改めたという説です。
明治維新後、政府は新しい時代にふさわしい地名表記を整える中で、“反乱”を連想させる字を避けたといわれています。
② 「阪」は「坂」と同じ意味を持つ地名用字
「阪」という字は、「坂」と同じく“さか”を意味する漢字で、地名などによく使われます。
「阪神(はんしん)」「阪南(はんなん)」など、関西地方では古くから馴染みのある表記でした。
また、「阪」は中国でも地形を表す漢字として使われており、「丘陵地の斜面」を意味します。
大阪の地形が“ゆるやかな坂の多い土地”であることからも、地名として自然な選択だったのです。
③ 「大阪」は“広く栄える地”という願いを込めた説
「大坂」は「大きな坂の地」という意味に加え、「大きく開けた土地」というニュアンスもあります。
「阪」に変わったことで、“反乱”のイメージを避けつつ、「大きく繁栄する都」という前向きな意味合いが強調されたと考えられています。
つまり「大阪」という字には、「新しい時代にふさわしい繁栄の都」という願いが込められているのです。
なぜ“坂”が多いのに「大阪」なの?
大阪は平地が多い印象がありますが、古代の地形をみると実は坂の多い土地でした。
上町台地(現在の大阪城周辺)は高台にあり、北と南にゆるやかな坂道が続いていました。
この地形が「大きな坂(大坂)」の由来といわれています。
江戸時代の地図にも「大坂町」と記載され、坂の多い街として知られていたのです。
「大坂」から「大阪」へ、地名に込められた時代の変化
江戸時代には商都として栄えた「大坂」ですが、明治維新後、「大阪」という表記に統一されることで
“新しい時代の日本を支える都市”という象徴的な役割を担いました。
いまでは「大阪府」「大阪市」として全国的に定着し、その“阪”は関西文化の象徴でもあります。
まとめ:「大阪」の“阪”は新しい時代の象徴
「大阪」の“阪”は、単なる表記の違いではなく、時代の節目を象徴する文字です。
「士が反(そむ)く」ことを避け、平和と繁栄を願った“阪”という字には、明治の人々の想いが込められています。
地名の裏側には、歴史と時代の移り変わりが隠されているのです。
👇じゃらんでお得に宿を探す!👇
![]()
👇楽天トラベルでお得に宿を探す!👇
![]()

“天下の台所”の歴史を感じながら、今の大阪を楽しんでみてください。
当ブログでは、旅行にまつわる疑問などを分かりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。