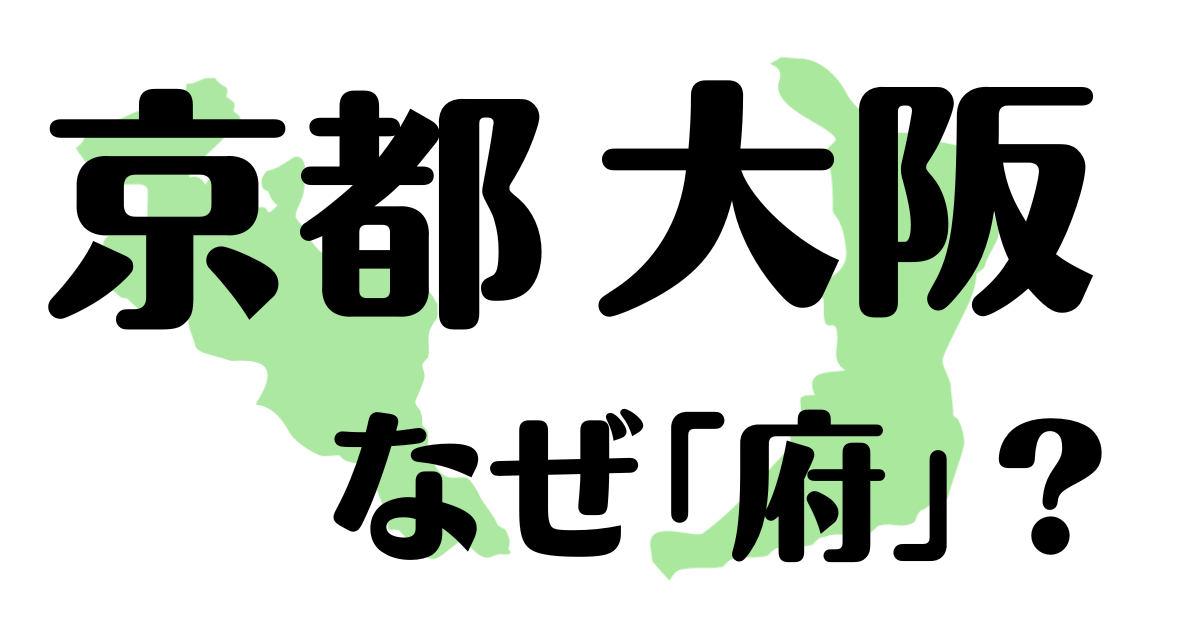日本の都道府県の中で、「府」がつくのは「京都府」と「大阪府」だけ。
なぜこの2つの地域だけ“府”なのか、他の県とは何が違うのか気になりますよね。
この記事では、「府」と「県」の違い」「“府”の意味」「なぜ京都・大阪だけが特別なのか」を歴史的背景とともに詳しく解説します。
そもそも「府」とは?

大阪府・様々なグルメが集う「道頓堀」
「府」という言葉は、もともと中国の行政区画から来ています。
古代中国で「府」は政治や軍事の中心地を指していました。
日本でも奈良時代以降、政府や軍の本拠地を「府」と呼ぶことがあり、
明治時代に近代的な行政制度が導入されたとき、「府=中心都市」「県=地方」として区分されました。
明治初期は「府」はもっと多かった!
実は明治維新直後、日本全国には「東京府」「京都府」「大阪府」「奈良府」「堺府」など、10以上の“府”が存在していました。
しかし、明治9年(1876年)の「府県統合令」で行政の簡略化が進み、
多くの府は「県」に統合され、最終的に京都府・大阪府・東京府の3府体制に。
その後、戦後の1943年に「東京府」は「東京都」となり、現在の2府体制が誕生しました。
なぜ京都と大阪だけが“府”として残ったの?
京都と大阪が「府」として残った理由は、どちらも政治・経済の中枢だったからです。
・京都府:平安京以来、天皇と朝廷が置かれた日本の首都。
・大阪府:江戸時代以降、「天下の台所」と呼ばれた経済の中心地。
つまり、「府」は日本の中心都市という意味合いを持つ特別な行政区分だったのです。
「府」と「県」の違いとは?
現在の日本では、法的には「府」と「県」に行政上の違いはほとんどありません。
地方自治法上はどちらも「都道府県」として同格に扱われています。
ただし、歴史的な経緯から、京都府・大阪府は文化的にも行政的にも
“中心都市”の象徴として特別な地位を保っています。
大阪府には「堺市・豊中市・吹田市」などの大都市が集まり、
京都府には「京都市」という千年の都があり、政治と文化の中核を担ってきました。
「府」と「都」の違いも気になる!
「府」と「都」もよく比較されますが、こちらも法的な違いはほとんどありません。
ただし、「東京都」は1943年に「東京府+東京市」を統合して生まれた特別な自治体で、都知事が市町村を包括的に統治するという点が、他の府県と異なります。
言い換えれば、「府」は地方中心都市、「都」は国家中枢という位置づけなのです。
京都・大阪の“府”が今も特別な理由

京都府・日本を代表する世界遺産「金閣寺」
京都は歴史・伝統・文化の象徴、大阪は商業・経済の中心地。
どちらも日本を代表する都市であり、「府」という呼称は今もその誇りを示しています。
この“府”という言葉には、「古都の威厳」と「商都の力強さ」が込められているのです。
まとめ:「府」は“都に次ぐ中心地”の象徴
「京都」「大阪」が“府”である理由は、単なる名前の違いではなく、
古代から続く日本の政治・文化・経済の中枢であった証です。
現在は行政上の差はなくなっても、地名の中に残る「府」には、
日本の歴史と誇りが今も息づいているのです。
👇京都・大阪のホテルを探す👇
![]()
👇 京都・大阪のホテルを探す 👇
![]()
古都の情緒や都会のエネルギーを感じる旅を楽しんでみましょう。
当ブログでは、旅行にまつわる疑問などを分かりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。