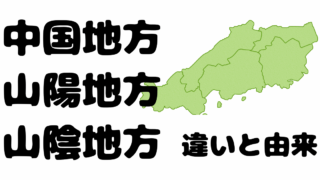駅前に神社が多いのはなぜ?

全国の駅を歩いていると、駅前やすぐ近くに小さな神社や稲荷を見かけることがあります。
「なぜこんなところに?」と思うかもしれませんが、実はこれには日本独自の信仰と鉄道の歴史が深く関係しています。
この記事では、駅前に神社が多い理由と、そこに込められた意味を詳しく解説します。
① 鉄道建設時の「土地の守り神」としての役割
明治時代、鉄道が全国に整備され始めたころ、人々は「新しい線路を通すと土地の神様が怒る」と信じていました。
そのため、鉄道の安全を祈願するために、線路沿いや駅前に神社や稲荷を祀る習慣が生まれたのです。
こうした信仰が、のちに「駅前の神社」として定着しました。
② 稲荷神は“商売繁盛”と“交通安全”の神
駅前に特に多いのが「お稲荷さん(稲荷神社)」です。
稲荷神はもともと五穀豊穣の神として信仰されていましたが、江戸時代以降は商売繁盛の神としても広まりました。
駅前には多くの商店が集まるため、「商売繁盛」「旅の安全祈願」といった願いを込めて祀られたのです。
③ “駅”=“新しい街”の守り神として
鉄道駅ができると、その周辺は新しい街として発展していきました。
当時の人々は「新しい街には神様が必要」と考え、土地の守護神として神社を建てました。
これが「駅前神社」のもう一つの由来です。
今でも多くの駅前には、その地域の人々が大切に守り続ける小さな社が残っています。
④ 鉄道関係者に信仰される“鉄道神社”も
中には、鉄道関係者や乗務員たちが安全祈願を行うために設けた「鉄道神社」もあります。
代表的なのが、京都・稲荷駅近くの「伏見稲荷大社」。
鉄道会社の多くが参拝しており、「安全輸送祈願祭」が毎年行われています。
全国の駅前で見られる代表的な神社
- 京都駅前: 梅小路稲荷神社(鉄道博物館近く)
- 上野駅: 上野東照宮(交通安全祈願にも人気)
- 大阪駅: 綱敷天神社(地元の守り神)
- 金沢駅: 金沢神社(学業成就・交通安全)
駅前神社は小規模ながら、地元の人々にとっては「旅の無事を祈る場所」として今も大切にされています。
駅前神社はパワースポットとしても人気!
近年は、駅前神社が「パワースポット」として注目されることも増えています。
旅行中のちょっとした立ち寄り場所として、また旅の安全を祈る習慣としても人気です。
特に稲荷系の神社はフォトジェニックな赤い鳥居が映えるため、SNS映えスポットとしても話題になっています。
まとめ
駅前に神社や稲荷が多いのは、偶然ではなく、
鉄道の安全祈願や商売繁盛を願う日本人の信仰心が形になったものです。
次に駅を訪れたときは、その小さな社に手を合わせて、旅の安全を祈ってみてはいかがでしょうか。
当ブログでは、旅行にまつわる疑問などを分かりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。